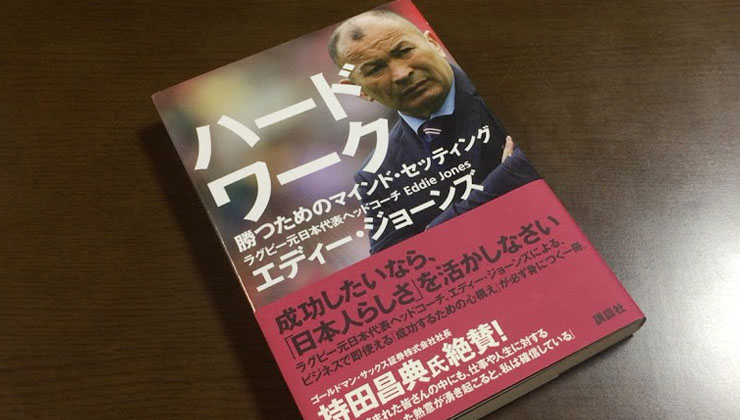ラグビー元日本代表ヘッドコーチのエディー・ジョーンズさん(以下ジョーンズHC)の本です。
「スポーツ史上最大の番狂わせ」と言われた2015年のワールドカップ南アフリカ戦の逆転勝利。
その指揮を取っていたのがジョーンズHCです。
ワールドカップで過去に1勝しかしたことがなく、その1勝も20年以上も前のもだったラグビー日本代表。
その日本代表が、日本を世界9位、2015年のワールドカップでは3勝を上げるまでに引き上げたときに指揮を執ったのがジョーンズHCです。
五郎丸選手もこのワールドカップで一躍時の人になりましたよね。
指揮する人によってここまで成果が変わるというところに興味を持ったので本書を手に取りました。
どんな本?
ジョーンズHCのチームを率いる考え方を、2015年ワールドカップに即して書かれた本です。
体格では他国の大型の選手に見劣りする日本人。その日本人の特性に合わせたチームビルディングが書かれています。
本書のキーワードは「ジャパン・ウェイ」。日本人の長所を最大限に活かし、短所を長所に変えることで、実力以上の力を発揮させる、エディーHCのアプローチです。
題材としてはラグビーですが、特性を活かして弱者が強者に立ち向かうところなど、普段の仕事に通じる考え方です。
短所は長所にもなりえる
ジョーンズHCが就任して最初に選手たちに言ったのが、「君たちは、これから世界のトップ10に入る!そして、3年後のワールドカップに、必ず勝つ!」
その時の選手の反応は、白けた顔のまま、誰も同意してくれなかったそうです。
ラグビーは体がぶつかり合うスポーツなので、体格で劣る日本人には勝てるわけがないといった価値観が蔓延していたからです。
この日本人選手の「自分たちは弱い」という思い込みを取り除き、「ジャパンウェイ」という日本人らしさを活かすスタイルを植え付けました。
あらゆる物事には、長所と短所があり、2つは表裏一体になっていることが少なくありません。
体が大きいということは、力強いという半面、動きが鈍くなります。
体が小さいということは、力の面では劣りますが、機敏な動きができるということです。
短所は長所になることが多く、短所にこそ、逆転のヒントが隠されています。
向上心のない努力は無意味
物事に懸命に取り組むことを「ハードワーク」と言います。
「ハードワーク」は、日本語で言う「頑張る」とは、少し意味合いが違います。
100パーセントの努力を傾けることと、それに加えて「今よりよくなろう」とう意識が必要です。
その意識がなければ、頑張りは無駄になります。
いくら頑張っても結果が出ない人は、間違いなく、「今よりよくなろう」という意識が欠けているからです。
本書ではこの文章が一番心に響きました。
自分の中で、一生懸命働くことをハードワークといった定義をしていましたが、「今よりよくなろう」という視点が抜けていました。
「今よりよくなる」という意識がないと単純に頑張るだけになってしまいます。その結果、消耗してしまったり成長が鈍くなったりしてしまうことに。
努力をしているつもりでも、実りのある努力にはなりません。
努力をするなら100パーセントの努力。
そしてそれは、「体力的なハードウェアの部分」と「思考的なソフトウェアの部分」の両方を伴う必要があります。
高みを目指すなら70パーセントの努力は無駄。100パーセントの本気さと「今よりよくなろう」という向上心が大切です。
心の底から好きか
ジョーンズHCのコーチの師匠がボブ・ドワイヤー氏だそうです。
ドワイヤー氏はオーストラリア代表のヘッドコーチです。
彼はゲーム中の細かいところまで覚えていて、どんな小さなことであったとしても論評できるそうです。
なぜこういったように記憶力がいいかというと、ラグビーが心の底から好きだから。
いくら記憶力がいいといっても好きじゃなければ厳しいですよね。
何かに秀でようとして、それがとんでもないレベルであったとするならば、好きであることは絶対条件。
もし心の底から好きと言えないのであれば、好きになるように努力することが大切だと思いました。
まとめ
スポーツにしてもビジネスにしても、自分たちの持ち味を活かした戦い方が大切です。
弱者が強者と同じ戦い方をしても勝ち目がありませんが、視点を変えると見えてくるものが違ってきます。
それは、弱者が弱みだと思っていたことも、裏返してみると強者が持っていない強みになるということ。
目標を掲げて、それを達成するためにはどうしたらいいか?
それは、マイナス思考を取り除き、自分たちはできると信じること。
そして、信じた未来に向かって100パーセントの努力をすることです。
できることは全部やる。
自分と相手の戦力を把握、特性を活かした戦略立案、行動計画と実行。
コントロールできることとできないことを見極めて、できることにフォーカスして走り続ける。
そうしたときに初めて世界に通じる扉が開けるのだと思いました。